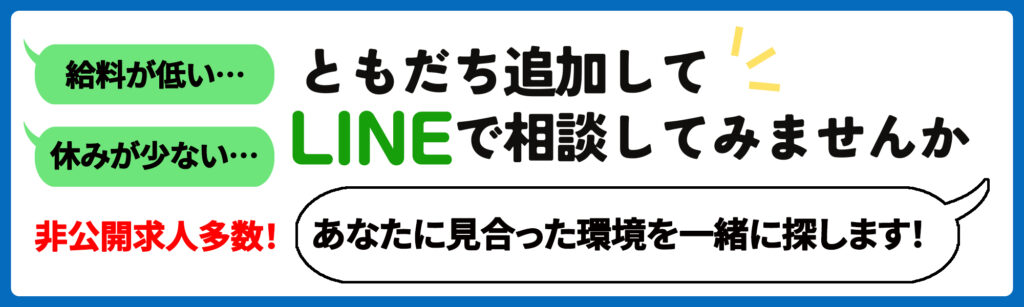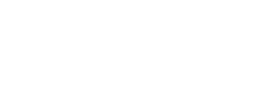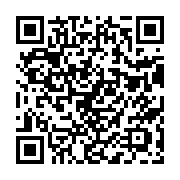3級自動車整備士の資格は、自動車整備士を目指すための第一歩目となる国家資格であり、多くの方が受験しています。
この記事では3級自動車整備士の業務内容や資格取得の流れ、試験難易度について解説します。これから整備士を目指したいと思う方は是非参考にしてみてください。
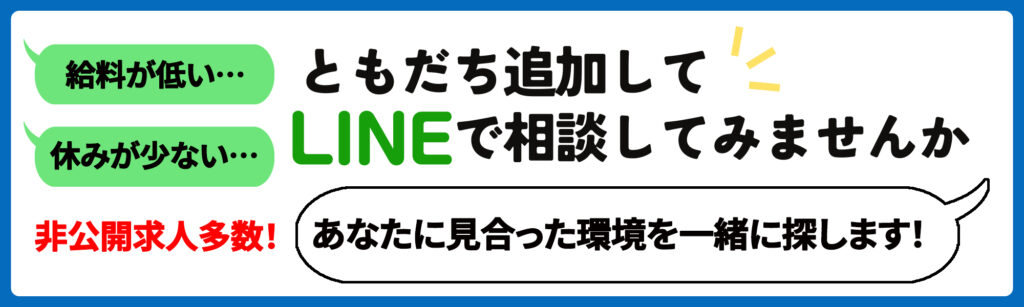
3級自動車整備士とは?
3級自動車整備士とは、普通自動車、四輪・三輪の小型自動車、四輪・三輪の軽自動車、二輪自動車、原動機付自転車の基本的な整備を行うために必要な資格です。
点検やタイヤ交換、オイル交換、ステアリングやブレーキの調整などが主な作業で、エンジンや足回りの分解整備など、より専門的な作業を行うためには上位資格である2級自動車整備士の資格を取得する必要があります。
3級自動車整備士資格の種類

3級自動車整備士資格には4種類あります。
3級自動車ガソリン・エンジン整備士
「3級自動車ガソリン・エンジン整備士」は、ガソリン・エンジンの構造や仕組みの知識が必要とされる資格です。自動車科のある高校や専門学校ではガソリン・エンジン整備士を目指すことが多く、受験者数も1番多い傾向にあります。
3級自動車ジーゼル・エンジン整備士
「3級自動車ジーゼル・エンジン整備士」は、ディーゼル車のエンジン整備が行える資格です。ガソリン・エンジン整備士の資格を持っていればディーゼル車の整備もできますが、この資格はディーゼル自動車に関するより専門的な知識を体系的に学べます。
3級自動車シャシ整備士
「3級自動車シャシ整備士」は、普通自動車、四輪・三輪の小型自動車、四輪・三輪の軽自動車のシャシ部分(自動車のボディやエンジンを除いた箇所)の基本的な整備を行うことが出来る資格です。
こちらも、ガソリン・エンジン整備士の資格を持っていればシャシの整備ができますが、シャシ整備士の資格ではより高度な知識・技術が身につきます。
また、サスペンションなどの足回りが多く、ステアリングやタイヤ関係の知識が必要になります。
3級二輪自動車整備士
二輪自動車整備士は、二輪自動車の整備や点検を行う際に必要な資格です。3級整備士の資格の中では最も合格率が高いとされている資格であり、3級自動車整備士資格の中でも保有率が高い傾向があります。
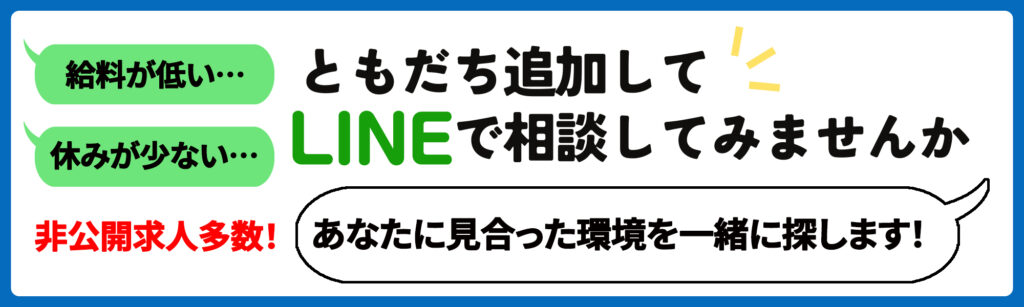
3級自動車整備士になるには?

3級自動車整備士は国家資格であり、誰でも受講できるわけではありません。資格試験を受講するためには、一定の条件を満たす必要があります。
以下より3級整備士資格の受講条件と資格取得の流れを解説します。
3級試験の受講条件
3級整備士資格の受講条件は、それまでの学歴によって異なります。
- 普通科などの自動車関係・機械関係以外の高校を卒業した方:実務経験1年以上
- 機械関係の学校(大学、専門学校、高校)を卒業した方:実務経験6ヶ月以上
- 自動車関係の学校(高校、専門学校)を卒業した方:卒業と同時に受験可
最短で資格を取得したい場合は、自動車科のある高校で、3級自動車整備士の実務免除となる一種養成施設に入るのがおすすめです。
専門学校では、2級自動車整備士資格を取得することが一般的であり、普通科等の学校を卒業した場合は、訓練施設で実務を受講する、または実務が行える職場で働く必要があります。
資格取得までの流れ
資格を取得するまでの流れとして、以下4つのステップがあります。
STEP1.各都道府県の整備士振興会に受講申請を行う
各都道府県に自動車整備振興会の拠点があるため、そこで受講申請を行います。
【申請時に準備するもの】
- 登録試験受験票
- 受験手数料
- 証明写真
- 郵便ハガキ(学科試験のみの場合2枚、実施試験の場合4枚)
- 受験資格を証明するもの(卒業証書や実務経験証明書)
STEP2.自動車整備技能登録試験に受講して合格する
学科試験は筆記試験となっており、4択から選ぶ形式となっています。実技試験については、実技試験を試験会場で行う場合もありますが、一種養成施設や自動車整備士振興会の技術講習を受け免除するのが一般的です。
一種養成施設では3級自動車整備士養成課程では教育時間が900時間と定められています。
※入校資格は中学卒業以上で期間は1年以上必要です。
STEP3.各都道府県の自動車整備振興会で全免申請の手続きを行う
全免申請とは一定の条件を満たすことで国土交通省が行う検定試験が免除となり整備士の資格を取得できる制度です。
学科や実技どちらかが合格した場合は2年間、検定試験が免除されるので実技を終えることができたら2年間の間に筆記試験に合格する必要があります。
【申請時に準備するもの】
- 各都道府県の自動車整備士振興会の検定申請書
- 学科試験合格申請書または学科試験合格通知ハガキ
- 整備技能講習修了証書または一種養成施設卒業証書
- 郵便はがき 2枚
- 実務経験が短縮になる方は、その卒業証書
- 実務経験証明書もしくは検定申請書
- 印鑑
- 申請料
STEP4.3級自動車整備士の合格証書が発行されたら資格取得完了
3級自動車整備士の合格証書が届き次第手続きは完了となります。
合格証書は再発行してもらうことができないため、失くさないように気をつけましょう。
3級自動車整備士の試験概要
| 学科試験 | 実技試験 | |
| 日程 | 第1回:10月/第2回:3月 | 第1回:1月/第2回:8月 |
| 出題数 | 30問 | 3問 |
| 出題形式 | 4択のマークシート | 実技 |
| 合格条件 | 70%(21問)以上の正答 | 各問題で40%以上の成績 |
| 試験内容 | ・構造/機能と取り扱い方法の初等知識 ・点検/修理/調整の初等知識 ・整備用の試験機/計量器と工具の構造/機能と取り扱い方法の初等知識 ・材料と燃料油脂の性質と用法の初等知識 ・保安基準その他の自動車の整備に関する法規 | ・簡単な基本工作 ・分解/組み立て、簡単な点検と調整 ・簡単な修理 ・簡単な整備用の試験機/計量器と工具の取り扱い |
試験内容は、エンジンの構造や機能などの一般的な知識から始まり、整備を行う時の点検や修理の知識、ガソリンの性質や保安基準に対しての法規などがあります。
実技試験の内容は、簡単な基本工作から部品の分解・組み立てを行い、その後簡単な点検・調整を行います。このとき、調整に使われる精密器具を落とす、もしくは雑に扱うと減点の対象となるため注意しましょう。
試験時間に対して内容が多いため、時間のかかる点検や調整の時間配分を長くする方法がおすすめです。
3級自動車整備士の合格率と難易度

3級自動車整備士の合格率は約6~7割であまり難しくはありません。教科書を読み込んだり過去問を何度も繰り返し解いたりすれば、問題なく合格できるでしょう。
以下、種類ごとの過去5年間の受験者数と合格率です。
【3級自動車ガソリン・エンジン整備士】
| 【年度別】 | 【受験者数】 | 【合格率】 |
| 2018年 | 4,229人 | 63.8% |
| 2019年 | 4,043人 | 71.1% |
| 2020年 | 4,172人 | 77.9% |
| 2021年 | 3,801人 | 74.7% |
| 2022年 | 4,008人 | 71.9% |
【3級自動車ジーゼル・エンジン自動車整備士】
| 【年度別】 | 【受験者数】 | 【合格率】 |
| 2018年 | 981人 | 63.2% |
| 2019年 | 875人 | 64.6% |
| 2020年 | 759人 | 72.2% |
| 2021年 | 832人 | 71.5% |
| 2022年 | 709人 | 60.6% |
【3級自動車シャシ整備士】
| 【年度別】 | 【受験者数】 | 【合格率】 |
| 2018年 | 2,167人 | 53.2% |
| 2019年 | 2,151人 | 57.4% |
| 2020年 | 1,798人 | 76.4% |
| 2021年 | 1,947人 | 66.7% |
| 2022年 | 1,799人 | 63.8% |
【3級二輪自動車整備士】
| 【年度別】 | 【受験者数】 | 【合格率】 |
| 2018年 | 256人 | 71.9% |
| 2019年 | 243人 | 68.7% |
| 2020年 | 214人 | 82.7% |
| 2021年 | 294人 | 85.4% |
| 2022年 | 245人 | 84.1% |
まとめ
自動車業界に特化している「タウ転職」では、3級自動車整備士を募集している求人や3級自動車整備士の資格を活かせる整備士以外の職種を取り扱っています。自動車業界の転職をお考えの方は、是非タウ転職を活用してみてください。