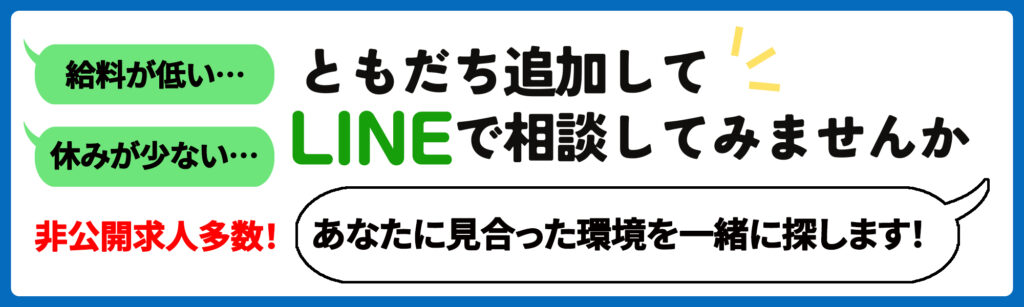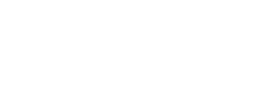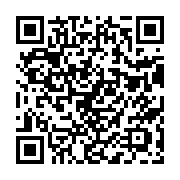自動車整備士として仕事をするには資格を取得しなければなりませんが、それには一定の条件を満たす必要があります。
この記事では、自動車整備士になる方法や必要な資格、資格の取得方法について解説していきます。また自動車整備士に向いている人の特徴についても解説しているため、参考にしてください。
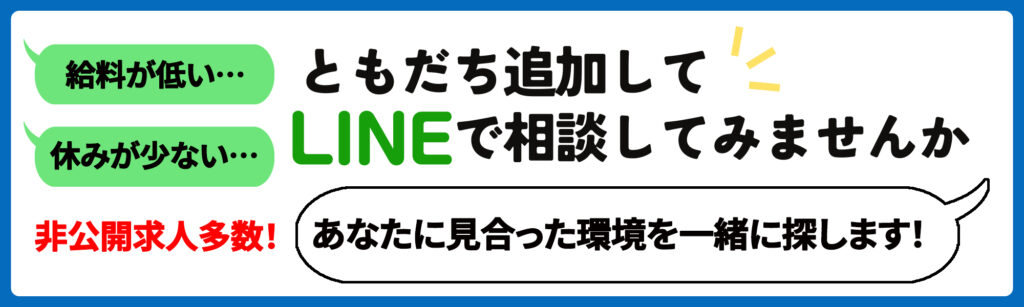
自動車整備士とは?
自動車整備士とは、自動車の点検・整備・修理を行う国家資格を保有した人のことをいいます。
主な業務内容は以下の3つと、その他オイル交換やタイヤ交換などがあります。
点検整備は、自動車の保守管理を目的に行う業務のことです。車をもっている方は、自動車の安全性を保つために車検や定期点検などが義務付けられているため、資格を持った自動車整備士が行います。
分解整備は、エンジンやミッションなど自動車のなかでも特に重要なパーツを分解して整備・修理を行う業務です。分解整備は高い技術を必要とするため、国からの認可を得ている「認証工場」や「指定工場」でしか対応できません。
また緊急整備は、急を要する故障や事故を起こした自動車の整備・修理を行う業務です。エンジンや電気系統などを点検し、修理箇所があれば整備・修理を行います。
自動車整備士は未経験でもなれる?
自動車整備士の仕事には資格がなくてもできる作業があるため、無資格・未経験でもなれます。例えば、自動車の鈑金塗装やオイル交換、タイヤ交換などは無資格でも対応可能です。
ただし資格がない場合は、担当できる業務範囲が限られているため高い給与は期待できず、転職活動も困難になるため、自動車整備士として長くキャリアを積んでいくためには、必ず資格は取得しておきましょう。
自動車整備士の資格の種類

自動車整備士の資格には以下のような種類があります。
3級自動車整備士
3級自動車整備士の資格は、専門学校に通わずに整備士を目指す場合、必ず取得しなければなりません。3級には下記の4種類があります。
- 3級自動車ガソリン・エンジン整備士
- 3級自動車ジーゼル・エンジン整備士
- 3級自動車シャシ整備士
- 3級二輪自動車整備士
3級資格取得者の主な仕事内容は、タイヤやオイルの交換などです。また、カー用品の取り付けや点検業務なども担当できます。しかし、エンジンやブレーキの分解整備などの本格的な仕事には従事できないため、自動車整備士の仕事としては物足りないと感じる人もいるでしょう。
2級自動車整備士
2級自動車整備士は自動車整備に関するほとんどの業務に従事できるため、整備士資格の中でも特に取得率が高い資格です。2級自動車整備士にも3級同様に下記の4種類があります。
- 2級ガソリン自動車整備士
- 2級ジーゼル自動車整備士
- 2級自動車シャシ整備士
- 2級二輪自動車整備士
自動車整備士を本業に据えバリバリ活躍するためには、2級自動車整備士の取得は必須になります。
1級自動車整備士
1級自動車整備士は、2002年に新設された自動車整備士のなかで最上位の資格です。1級自動車整備士には、以下のような種類があります。
- 1級小型自動車整備士
- 1級大型自動車整備士
- 1級二輪自動車整備士
ただし、これまで試験が実施されたのは「1級小型自動車整備士」のみで、残りの2つは未だ実施されたことがありません。
また、現在の整備士業界では2級資格を取得すればほぼすべての業務ができるため、1級資格を取得している人はあまりいない傾向にあります。しかし1級を持っていれば、資格手当がある職場では給与アップを狙えますし、さらに、次世代型自動車に関する知識が身につくため、将来的な需要は確実に増してくるといえます。
特殊整備士
特殊整備士の資格は、特定のパーツ整備を専門とする資格です。主な種類として下記の3つがあります。
- 自動車タイヤ整備士
- 自動車電気装置整備士
- 自動車車体整備士
これらは、1級あるいは2級自動車整備士の資格を保持していれば作業できるため、特殊整備士は必ず取らなければならない資格ではありません。しかし、特殊整備士の資格を保有していると、そのパーツに対する専門知識や技術をさらに高められます。
自動車整備士になるには?

資格を取得する方法は、「自動車の専門学校に通って取得する方法」と、「自動車整備工場で実務経験を積んでから取得する方法」の2とおりです。
自動車整備士の専門学校に通って取得する
自動車整備士の専門学校は基本的に、4年制と2年制にコースが分かれています。
2年制の専門学校に通って資格取得を目指す場合、卒業後に2級自動車整備士を受験する資格を得られるため、そこで合格すれば、2級自動車整備士として仕事に従事することが可能です。さらにその後、3年間の実務経験を積めば1級自動車整備士の受験資格を得ます。
一方の4年制の専門学校の場合は、最初の2年間で2級合格を目指し、残りの2年で1級合格を目指します。
専門学校に通う場合、短期間で資格を取得できるというメリットがあります。
実務経験を積んでから取得する
国が認定した「認定工場」もしくは「指定工場」で実務経験を積んでから自動車整備士の資格を取得する方法もあります。ただしこのような場合、3級自動車整備士から順番に取得する必要があるため、専門学校に通って取得するよりも時間がかかります。
また、学歴や大学の学科によって自動車整備士を受けるのに必要な実務経験が異なります。
自動車科を卒業している場合は、卒業後すぐに3級自動車整備士の試験を受けることが可能です。3級自動車整備士の資格を取得後、2年間の実務経験を経て2級、その後3年間の実務経験を経て1級という流れです。
機械科を卒業している場合は、卒業後6ヵ月の実務経験を経て3級自動車整備士の試験を受けられます。3級自動車整備士の資格を取得したあとは、自動車科と同様に2年間の実務経験を経て2級、その後3年間の実務経験を経て1級という流れで取得できます。
上記以外の学科を卒業している場合は、卒業後1年間の実務経験を経れば、3級自動車整備士の試験を受けられます。3級自動車整備士の資格を取得後、3年間の実務経験を経て2級、その後3年間の実務経験を経て1級という流れで取得できます。
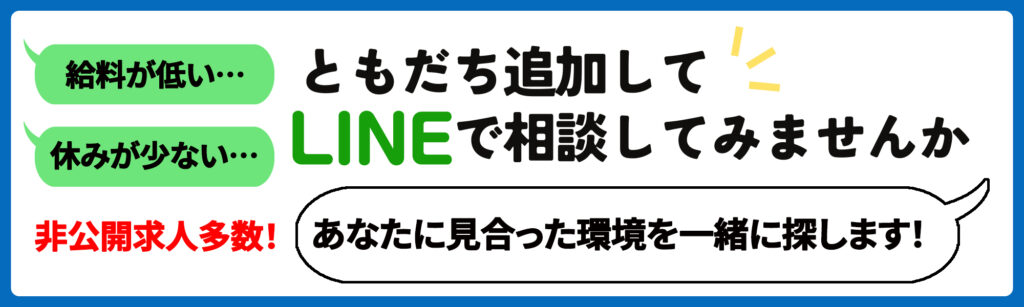
自動車整備士資格の難易度・合格率について

ここでは、3級~1級自動車整備士のそれぞれの難易度や合格率について解説していきます。
3級自動車整備士の難易度・合格率
3級の試験科目は学科と実技の2つがあります。
| 学科 | 実技 | |
| 試験時間 | 60分 | 30分 |
| 出題数 | 30問 | 3問 |
| 合格基準 | 21点以上 | 18点以上 |
学科試験の内容は基礎知識が大半です。また、保安基準に関する法規も含まれます。学科試験では、1問1点の問題が30問出題されます。マークシート方式で、試験時間は60分です。30点満点に対して、21点以上で合格できます。
一方の実技試験は、基本的な工作や調整・修理などがあります。こちらも学科同様に基礎的なものばかりです。学んだことが活かせるように準備しておきましょう。
2022年度に開催された3級自動車整備士試験の合格率は以下の通りです。
| 種 類 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| ガソリン | 4,008 | 2,881 | 71.9 |
| ジーゼル | 709 | 430 | 60.6 |
| シャシ | 1,799 | 1,148 | 63.8 |
| 二輪 | 245 | 206 | 84.1 |
2級自動車整備士の難易度・合格率
2級自動車整備士は3級自動車整備士と同様に、学科と実技の2種類あります。
| 項目 | 学科 | 実技 | |
| ガソリン・ジーゼル・二輪 | シャシ | ||
| 試験時間 | 80分 | 60分 | 30分 |
| 出題数 | 40問 | 30問 | 3問 |
| 合格基準 | 28点以上かつ分野ごとで40%以上 | 21点以上かつ、分野ごとで40%以上 | 36点以上かつ、分野ごとに40%以上 |
2級自動車整備士の試験は4種類とも4択のマークシート方式です。試験時間80分で、出題数は40問あります。ただし、2級自動車シャシ整備士のみ、試験時間60分で出題数30問です。
28点以上かつ、分野ごとで40パーセント以上の成績であれば合格です。自動車シャシ整備士は、21点以上で、分野ごとで40パーセント以上の成績で合格できます。
一方の実技試験は、基本工作や一般的な調整・検査・修理などがあります。整備用の機械や工具の使い方もあるので準備しておきましょう。
2022年度に開催された2級自動車整備士試験の合格率は以下の通りです。
| 種 類 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| ガソリン | 10,562 | 9,323 | 88.3 |
| ジーゼル | 8,134 | 7,835 | 96.3 |
| シャシ | 266 | 196 | 73.7 |
3級自動車整備士の試験よりも受験者数と合格率が高くなっています。
1級自動車整備士の難易度・合格率
1級自動車整備士の試験内容は、学科試験と実技試験、口述試験の3つがあります。
| 学科 | 実技 | 口述 | |
| 試験時間 | 100分 | 40分 | – |
| 出題数 | 50問 | 4問 | 2問 |
| 合格基準 | 40点以上かつ、分野ごとで40%以上 | 32点以上かつ、分野ごとに40%以上 | 16点以上 |
学科試験は、2級自動車整備士の知識をさらに踏み込んだ内容になっています。また、法規に関する知識も深堀りされています。試験は4択マークシートで、1問1点の問題が50問出題されます。試験時間は100分で、40点以上かつ、分野ごとの正解率が40パーセント以上あれば合格できます。
実技試験は、基本工作から点検・分解や修理、そして機器や工具の取り扱いです。試験時間は30分、40点満点で32点以上あれば合格できます。
また、1級自動車整備士では口述試験があることを覚えておきましょう。口述試験の内容は、当日にならないと分かりませんが、過去には「不具合を訴えているお客様への対応の仕方」や「点検・整備記録簿の作業内容の説明」などが出題されました。
口述試験は、問題数は2問で、1問10点です。20点満点に対して16点以上で合格です。
2022年度に開催された1級自動車整備士試験(1級小型自動車整備士)の合格率は以下の通りです。
| 種 類 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
| 一級小型(筆記) | 2,456 | 1,302 | 53.0 |
自動車整備士の資格を取得する流れ

ここでは、自動車整備士の資格を取得するまでの一般的な流れについて解説します。
STEP1.検定試験もしくは登録試験の受験を申請する
まずは、検定試験もしくは登録試験の受験を申請します。検定試験は国土交通省が実施しており、登録試験は各都道府県の自動車整備振興会が実施していますが、申請先はどちらでも問題ありません。ただし登録試験を受ける場合は、合格後、国土交通省に検定試験の免除申請を行う必要があります。
受験を申請する際には、以下のものを持参しましょう。
- 登録試験受験申請書
- 受験手数料
- 証明写真
- 郵便はがき
- 卒業証書や実務経験証明書(受験資格が証明できるもの)
卒業証書や実務経験証明書は、専門学校修了もしくは一定の実務経験を積めば発行してもらえます。
なお、自動車整備士の試験は、受験資格を満たしていなければ受験できません。受験資格を満たすためには、前述で解説した通り専門学校を修了するか、一定の実務経験を積む必要があるので注意しましょう。
STEP2.自動車整備士の試験を受ける
申請が完了したら、試験日に自動車整備士の試験を受けましょう。先述したように、一定の条件を満たせば一部の試験が免除されたり、試験自体が免除されたりするため、受験前に自身の受験範囲を事前に確認しておきましょう。
STEP3.自動車整備振興会で合格証明書の申請手続きをする
試験に合格したら、各都道府県の自動車整備振興会で合格証明書の申請手続きをします。この手続きに必要なものは、自動車整備振興会によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
以下は、申請手続きをする際に必要なものの一例です。
- 検定申請書
- 学科試験合格証書もしくは学科試験合格通知はがき
- 整備技能講習修了証書もしくは一種養成施設卒業証書
- 郵便はがき
- 3級自動車整備士合格証書(2級を受験した場合)
- 2級自動車整備士合格証書(1級を受験した場合)
- 実務経験が短縮になる場合はその卒業証書
- 実務経験証明書もしくは検定申請書
- 印鑑
- 申請料
2級自動車整備士または1級自動車整備士を受験した際は、その一つ前の級の合格証書を提出しなければなりません。ただし3級自動車整備士の場合は不要です。
また、自身が卒業した高校または大学によっても提出に必要な書類は異なるため、注意しましょう。詳しい内容については、各都道府県の自動車整備振興会へ問い合わせるのが確実です。
STEP4.合格証明書を受け取る
合格証明書が発行されるとはがきで通知が届くため、自動車整備振興会に取りに行きましょう。仕事で合格証明書を取りに行けないときは、自動車整備振興会へ相談すれば郵送してくれる場合があります。
自動車整備士に向いている人

自動車整備士に向いている人は、主に下記の特徴があげられます。
整備士の仕事は細かな作業が多く器用さが求められるため、そういった作業が好きな人は適性があるといえるでしょう。
また、地味で単調な作業が多いのも特徴で、特に仕事を始めたばかりの頃は、小さな部品と向き合う日々が続きます。このような地味な作業でも、嫌にならずに向き合える性格の方は、自動車整備士に向いていると言えます。
さらに、お客様に整備・修理を行った内容を説明したり、トラブルを防ぐためのアドバイスをしたりすることも自動車整備士の業務の一つです。そのため、人とコミュニケーションをとることが好きな方にも向いています。
まとめ
今回は、自動車整備士になるために必要な資格や取得する方法などについて解説しました。
自動車整備士への転職を検討中の人は、タウ転職へご相談ください。タウ転職では、自動車整備士をはじめ、自動車関連の仕事をご紹介しています。LINEでのご相談も受け付けているためお気軽にご利用ください。
公式のLINEアカウントにともだち登録すれば、就職・転職に関する相談を受け付けています。登録・利用は完全無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。